ここのところ忙しくて榊を交換する暇がないわけよ。
で、ちょっと教えて欲しいんだけど、そもそも榊を交換するタイミングって決まってるのかな?
正直、できるだけ交換頻度が少ないほうが助かるし。
日々のちょっとしたお世話で長持ちしてもらえたら助かるな。
お家に神棚を祀り始めたものの、榊のお世話に頭を悩ませることってありますよね。
罰当たりかもしれないけど、正直、できるだけ交換の頻度とか、お世話する手間が省ければありがたいなんて考えてしまったり…
実際、きつねも自宅の神棚の榊についてはいろいろと悩みましたね。
その結果、神主さんに本音ベースで相談したり。
そこで、この記事では、神棚の榊の交換時期について、神主さんから聞いたぶっちゃけ話なども織り交ぜながら、リアルなところを紹介していきたいと思います。
こちらの記事内容は、
- 榊はいつ交換すればいいのか
- 榊を長持ちさせる秘訣とは
- 交換後の処分はどうする
などでお届けします。
なお、こちらの記事は以下の書籍などを参考に作成しています。
- 神社検定公式テキスト①『神社のいろは』(扶桑社)
- 『なぜ成功する人は神棚と神社を大切にするのか?』(窪寺伸浩)<あさひ出版>
また、現役の神主さんにも監修してもらっています。
榊の交換時期
榊の交換時期については、
一般的に、毎月1日と15日に新しいものと交換すると良いと言われています。
というのも、神社では1年の間にたくさんの神事が行われてますが、毎月1日と15日には月次祭(つきなみさい)という神事が行われています。
で、この月次祭に合わせて、神棚に酒・野菜・果物などをお供えするのが一般的なお供えのタイミングとされていて、それに合わせて榊も交換すると良いと考えられてるからなんですね。
月次祭(つきなみさい):氏子、崇敬者の安泰や社会の安定、平和を祈る神事です。神社の中には毎月1日だけとか15日だけといったところもあります。
ただ、実際に榊のお世話をするようになるとわかるのですが、毎月1日や15日で交換するということになると、まだ榊が青々としてるのに交換のタイミングがきちゃったりするんですよね。
そもそも榊に元気がなくなるタイミングって、季節とか、水の交換頻度とかにめちゃくちゃ影響されます。
夏の暑い日が続いてるときに、水の交換をちょっとサボったりすると、1週間くらいで全部枯れてしまいますし、冬の時期に毎日水の交換をすると余裕で1か月とかもちます。
今きつね宅で飾っている榊はかれこれ2か月近く青々としたままです。
(秋の涼しい時期ですが…)
ということは、榊が枯れるタイミングと月次際が行われるタイミングは全く一致していないってことになります。
でもこれめっちゃ悩ましくないですか??
元気な榊を無理やり交換しなきゃいけないのかって…
きつね的にはここのところをちゃんと解決しておきたかったので、実際に神主さんに聞いてみることにしたんです。
巷では毎月1日と15日に交換するといいって言うじゃないですか。
そうなると、元気な榊でもその時期が来ると交換したほうが良いんですかね?
正直言って、元気な榊を処分するのって気が引けちゃうんですよね。
逆に、1日とか15日の前に榊が枯れてしまうことだってありますし…
ちなみに神社で飾る榊の交換頻度ってどれくらいなんですか?
しっかり根切りすれば余裕で1か月は持ちます。
もったいないのでそのままお使いください。
交換の目安は葉っぱがパラパラ落ちてきたら替え時です!
ちなみに、大手の神社ではこまめに変えてますが、そこは自宅とは別ということで気になさらずとも良いですよ。
※ここで言う根切りとは、榊の茎の根に近いほうを少し斜めに切りそろえることで、榊の水の吸収をスムーズに行わせることをいいます。
と、かなり実際的なアドバイスをいただくことができました。
しかも神主さんからも「もったいない」というお言葉が!
やっぱり、一般的な交換のタイミングにとらわれることなく、枯れてきたら交換する!ってことで、これがベストなタイミングになりますね。
どうやら「罰当たり」とか心配することもなさそうです。
ただ、きつねの経験上、榊は青々としたものを飾っておいたほうがご神威は高まるように感じてます。
なんというか、神棚からのパワーが全然違ってくるんですよね。
なので、榊の葉が枯れ始めたら、枯れ始めた葉だけを間引いて、全体としては青々としてる状態をキープするようにはしてますね。
だんだんと葉が減っていって、神棚が醸すパワーが落ちてきなと思ったタイミングで新しい榊と交換するようにしてます。
神主さんに常々言われているのは、
ということなので、形式的に榊をいつ交換するかを気にするよりも、日々の榊のお世話を通じて神棚のご神威をありがたく受け取っていくことを重視していきたいなと考えてます。
神棚のお酒の交換時期についても要チェック!

榊を長持ちさせる秘訣
さきほどもお伝えしましたけど、榊がどれくらい長持ちするかは、季節とか水替えの頻度とかによります。
(ここでは室温とか湿度とかも含めて季節として考えます。)
夏になると水替えをちょっとサボっただけで水のいたみが早くて、榊もすぐに枯れてしまいます。
榊がいたむ原因となる雑菌がすぐに繁殖しちゃうんですよね。
とはいえ季節そのものはコントロールできません。
(当たり前ですが)
なので夏になって水のいたみが早くて榊が早く枯れてしまうのは、ある意味仕方ないことだと思います。
そう考えると、結局、榊を長持ちさせるためにできるのは、水替えをいかに早くやるかに尽きるということになりそうです。
実際、きつねの経験上だと、長持ちさせるなら毎日水替えするのがベストです。
榊の持ちと水のいたみは連動しますから、水替えを最短でやるのが榊を長持ちさせることにつながるのは当然ですよね。
実は、一般的にも、神棚の榊は毎日水替えするのが良いとされています。
ただし、それは榊を枯らさないためというより、神棚にお供えする、米・塩・水の三品を毎日お供えするのにあわせて榊の水替えもするというものです。
たしかに、きつね自身も朝のバタバタする時間に水替えをしているので牛太郎の気持ちはよくわかります。
でも長持ちさせることを優先するなら、やっぱり水替えは毎日やるべきですね。
ただ、そのかわり、最短時間で水替えすれば良いのではないかと。
榊立ての洗浄までやってると大変なので、きつねの場合は、ホントに水替えだけを20秒くらいでちゃちゃっとやってます。
それでも、どうしても毎日の水替えがしんどいって場合はこちらから造花の榊も検討してみてください。
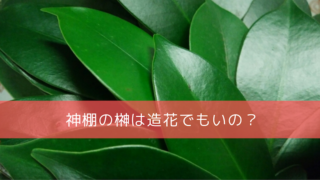
榊を長持ちさせる裏技
あと、きつね自身が全部やってるというわけではありませんが、少しでも榊を長持ちさせる裏技的なことを紹介します。
榊を長持ちさせるには、雑菌の繁殖をいかに抑えるのかがカギなので、
- 台所の漂白剤を一滴落とす
- 榊立ての底に10円玉を入れる
- 榊の茎のぬめりを取る
- 榊立てを洗うときにはしっかり除菌する
などの裏技がよいとされています。
このうちきつねが水の交換を毎日やらずにサボってたとき、たまの水交換で茎のぬめりをとることをやってました。
効果はあったような気がします。
10円玉がよいっていうのは理屈はわかります。
台所の排水部分に10円玉を置いておくと、たしかにぬめりがつきにくくなったりしますから。
ただ、きつね宅の神棚の榊立ては口が狭くて10円玉が入りません…
なので効果のほどは想像でしかありませんが、試す価値はあると思います。
漂白剤とか榊立の除菌については夏場やってみて、またブログで報告させてもらいますね。
ちなみに、さっきも出てきましたけど冬場は毎日水交換するだけで、めちゃくちゃ長持ちするので、ここまでいろいろと気をつかう必要もないかなと思います。
交換した榊の処分方法
榊の処分方法も悩ましいですよね。
いったんは神域を示すものであったり、神様が宿るものとして神棚に飾ったわけですから、ゴミとして処分するのはどうも抵抗があります。
ただ、処分方法についても正式な決まりというものはありません。
だから余計に悩ましいのですが…
一般的には、
- 川や海に流す
- 土に埋める
- 白紙に包んでゴミ箱に捨てる
- 塩をふって清めてゴミ箱に捨てる
- 神社に納めて焼いてもらう
という声が多いです。
きつねの処分方法は、枯れた榊を半紙に包んで生ゴミ用のゴミ箱に置いて塩をふりかけてフタをするというものです。
一般的な処分方法として紹介されているもののうち、
・白紙に包んでゴミ箱に捨てる
・塩をふって清めてゴミ箱に捨てる
この2つを包含するような処分方法ですね。
榊の処分方法について神主さんに確認してみると、
ただ、現代ではそうはいきませんので、塩で祓って捨てるというは良い処分方法ですね。
神社によって違うとは思いますが、私のいたところではきちんと焼却炉でお祓いし、お札と一緒にお焚き上げしておりました。
また、榊の森があるので周辺に埋める、ということもしていましたね。
ということなので、あくまで家庭での処分であれば、塩でお清めしてからゴミとして処分すればよいようです。
さらに丁寧に処分するなら、きつねと同じく、白い半紙に包んで処分するということになります。
まとめ
毎日お水を替えて、できるだけ長持ちさせてから交換するようにするわ。
そして神棚に常に青々とした榊が飾られていると、間違いなくご神威は高まるし、開運につながるしね。
この記事の内容をまとめると、
- 榊の交換時期には特にルールはない
- 葉が枯れて落ち始めたタイミングで交換すればよい
- 水替えを毎日すると榊も長持ちする
- 交換後の榊は塩をふって清めてからゴミ箱に捨てるとよい
となります。
それでは最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。
みなさんの開運を心より祈念いたします。
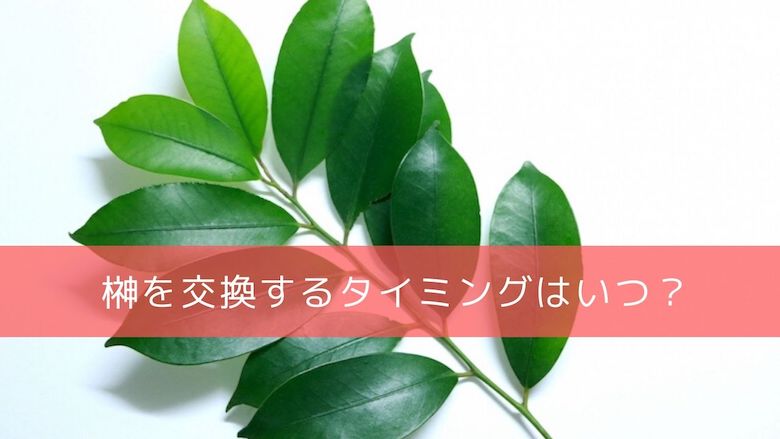


.jpg)



